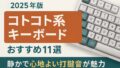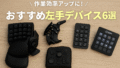※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれます。

EDIFIER MR4 実機レビュー|1年以上使ったリアルな感想
私にとって、MR4は人生初のモニタースピーカーでした。
それまで使っていたのはLogicoolの低価格帯PCスピーカーで、音質へのこだわりは特になく「聞こえればいい」という程度。
しかし、デスク環境づくりに熱中し始めた頃、「見た目も音もこだわりたい」と思うようになり、そこで出会ったのがこのEDIFIER MR4でした。
最初は「スピーカーに2万円近く出すなんて高い」と感じていましたが、実際に使い始めてからはその印象が180度変わりました。
ここでは、1年以上使ってわかったMR4の魅力と、最新モデルMR5との違いを正直にレビューしていきます。
MR5 vs MR4|価格とスペックの違い
| 項目 | EDIFIER MR5 | EDIFIER MR4 |
|---|---|---|
| 方式 | 3ウェイ/トライアンプ/デジタル処理(DSP、DRC、アクティブクロスオーバー) | 2ウェイ/アクティブ(モニター&音楽モード切替) |
| ユニット | 5インチウーファー+3.75インチミッド+1インチシルクドーム | 4インチウーファー+インチ″シルクドーム |
| 周波数特性 | 46Hz–40kHz(フラットレスポンス) | 60Hz–20kHz |
| 定格出力 | 合計110W RMS(@1m最大101dB) | 21W+21W RMS(合計42W) |
| 入力端子 | バランスXLR/バランスTRS/RCA/AUX、前面ヘッドホン | バランスTRS/RCA/AUX、前面ヘッドホン |
| ワイヤレス | Bluetooth(Hi-Res Wireless、LDAC対応/Bluetooth 6.0) | なし(有線専用) |
| 国内実売の目安 | 約¥34,000〜¥44,000前後 | 約¥15,000〜¥18,000前後 |
| 想定ユーザー | 制作+リスニングを高次元に両立。Bluetoothも活用したい人 | 初めてのモニター/有線で堅実にコスパ重視の人 |
開封と第一印象
パッケージから取り出した瞬間に感じたのは、想像以上の高級感でした。
シンプルで無駄のないデザインはデスクに置くだけで雰囲気を一段引き締めてくれます。特にマットな質感と角の処理が上品で、価格以上の仕上がりだと感じました。
本体はそれなりに存在感があります。といっても、モニタースピーカーとして考えると普通、むしろ少し小さめ程度でしょう。デスクの見た目にこだわる人にとっても、このサイズ感は大きな魅力だと思います。
MR4を1年以上使って感じた「強み」
聴きやすく疲れにくいバランス
- 低域:ずんずん響く心地よさ。EDMやポップスとの相性は抜群で、ベースラインが楽しく聴ける。
- 中域:ボーカルの明瞭さや楽器の分離感は十分。声が埋もれにくく、トーク系コンテンツとの相性も良い。
- 高域:一部の楽曲ではややシャリ感を感じることもあるが、背面のダイヤルで調整可能。高音域の存在感はしっかりあり、総合的には満足度が高い。
- 静音性:ホワイトノイズはほぼなし。夜間でも違和感なく使える静けさがある。
モニタースピーカーらしい素直さを保ちつつ、日常のリスニングでも快適。BGMから映画・配信視聴まで「万能のちょうど良さ」を感じます。
デスク映えするミニマルな筐体と設置自由度
マットブラック基調のシンプルでコンパクトなデザインはワークデスクに馴染みます。
スタンドやインシュレーターと併用すると定位と奥行きが改善し、価格帯以上の密度感を狙えます。
操作/接続のストレスが少ない
- 前面ノブで音量・電源・モード切替が直感的
- 前面ヘッドホン出力が便利(夜間や会議前のチェックにも)
- バランスTRS/RCA/AUXでPC・インターフェース・TVまで柔軟に接続
- 背面にあるBASSとHIGHのダイヤルで好みに応じてチューニング可能。自分好みに追い込める柔軟さが魅力


MR5とMR4の「音」比較|3ウェイ&大出力 vs 小型&素直なバランス
まず結論から。
低域の厚み・音圧・ダイナミクスはMR5が一段上。中〜高域の素直さと聴きやすさ、そして価格対効果はMR4が魅力です。以下、客観情報と実聴インプレッションをあわせて整理します。
設計差が生む音のキャラクター
- MR5:5インチWoofer+3.75インチMid+1インチTweeterの3ウェイ・トライアンプ構成。デジタル処理(フルDSP/3ウェイ・アクティブクロスオーバー/DRC)で46Hz〜40kHzのフラットレスポンスを謳い、合計110W RMS・最大101dBの余裕ある出力で近接〜小リビングまで対応。Bluetooth(LDAC)対応でワイヤレス再生でもレンジを確保。
- MR4:4インチWoofer+1インチTweeterの2ウェイ構成。公称60Hz〜20kHz、21W+21Wの出力。測定レビューでは小型ゆえに超低域は控えめだが、中域の聴きやすさと全体の素直さが評価されています。
低域:量感・伸び・分離
- MR5:口径アップと専用ミッド帯域の分担で低域の量感と分離が向上。MR4に比べて低域が明瞭で、音量を上げた時のロー~ミッドの厚みが増し、レイヤー分離が良い印象で、EDM/ロック/映画BGMで恩恵を感じることができます。
- MR4:小型らしく超低域の伸びは控えめだが、タイトで過剰にならないバランス。測定では70Hz付近まで比較的フラットで、軽いEQや設置工夫で体感的な厚みを稼げる余地があります。
中域:情報量と前後感
- MR5:ミッド専用ユニットとトライアンプで中域の見通しが良く、ボーカルやギターの分離・定位がクリア。音量を上げても中域の質感が崩れにくいです。
- MR4:素直で聴きやすい中域。制作の「厳密さ」を突き詰めるより、日常のリスニングで心地よく前に出るボーカルを楽しめるキャラクターという印象です。
高域:伸び・質感・“刺さり”
- MR5:公称40kHzまでのレンジとDSP最適化により、高域の伸びと滑らかさが感じやすい。ぬくもりのある耳当たりが良い音です。
- MR4:一部楽曲でシャリ感が出る場合もあるが、背面のBASS/HIGHトーンで追い込み可能。価格帯を考えると十分にクリアな音です。
ダイナミクスと音圧感
音量を上げた時の余裕は明確にMR5。110W/最大101dBのヘッドルームは、近接リスニングでも瞬発力とレイヤー分離に効いてきます。MR4は近接〜小音量での整ったバランスが魅力で、作業BGMや深夜視聴との相性が良いです。
用途で選ぶなら
| シーン | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| EDM/ロック/映画BGMで迫力重視 | MR5 | 低域の量感と分離、ダイナミクスの余裕 |
| ボーカル中心のJ-POP/アコースティック | MR4 | 中域の聴きやすさと素直なバランス |
| 制作(ミックス確認)と普段使いを両立 | MR5 | 3ウェイ&トライアンプで帯域分担が正確 |
| 省スペース/深夜の小音量リスニング | MR4 | 小型・低ノイズ・前面HP端子で実用的 |
GENELEC G ONEとの比較|価格帯は違えど感じた音の違い
価格帯が大きく異なるため直接のライバルではありませんが、参考として記載しておきます。
MR4をしばらく愛用した後、私はさらに音質を追い求めてGENELEC G ONEを導入しました。結果として、次のような違いを強く感じました。

高音の解像感と空気感
G ONEの解像度や空気感は圧倒的で、MR5をも凌ぐレベル、弦楽器やピアノの響きが一段上のリアリティを持っています。
ただし、G ONEを知らなければMR4でも十分に満足できるレベルの高音であることは間違いありません。
低音のキャラクター
タイトで締まりがあり、モニター用途らしい精度の高い低音。クラブ系やクラシックなど音の正確さを求めるジャンルで真価を発揮します。
全体のバランス
G ONEはモニタースピーカーとしての完成度が非常に高く、制作現場でも信頼されるだけの実力を持っています。
一方でMR4は「価格以上に楽しめる音」が大きな魅力。2万円未満という価格帯を考えると、コストパフォーマンスの差は歴然です。
デザインと存在感
個人的な好みですが、デスクに置いたときの存在感はMR4やMR5に軍配が上がります。
G ONEのような小型スピーカーは実用性が高く優秀ですが、MR4やMR5は「音を鳴らしている感」が見た目からも伝わり、所有欲を満たしてくれます。
クラシックで感じた大きな差
特にクラシック音楽を聴いたときに両者の違いが顕著に表れました。
バイオリンの響きやホールの残響の表現力はG ONEが圧倒的で、「この音を知ってしまったらもう戻れない」と評されるのも納得です。
結論として、音質の絶対値ではG ONEが圧倒的です。しかし、MR4は「価格を大きく超える楽しさ」を提供してくれるスピーカー。
初めてのモニタースピーカーやデスク用リスニングならMR4で十分満足できる、というのが私の実体験です。

MR5登場でMR4の価値は下がったのか?
2025年に登場したEDIFIER MR5は、トライアンプ構成・LDAC対応Bluetooth・110W RMSという進化を遂げたモデルです。ただ、MR4との関係を「価値が下がった」と見るかは見解が分かれるポイントです。
総合的な判断:MR4の「価値の変化」まとめ
- MR5は確かに性能面で大きく進化しており、制作・高音質再生・アプリ調整・ワイヤレス利便性などが大幅に向上しています。
- 一方で、MR4は「価格帯」「音の品質」「シンプルさ」といった点で、依然として優れた選択肢としての立場を保っています。
- つまり、価値自体は下がっていない。むしろ、ニーズに応じてどちらがよりお得かを考えて選べる状況になっているといえます。
結論としては、MR5の登場によってMR4の価値が本質的に下がったわけではありません。Bluetoothや高出力が必要な人にはMR5が魅力的ですが、逆に有線で十分・価格を抑えたい人にはMR4は今も「買い」という判断が有効です。
MR4はこんな人におすすめ
- 初めてモニタースピーカーを購入する人
- Bluetooth機能は不要で、有線接続が前提の作業環境の人
- ポップス、ロック、EDMなどのリスニングを重視したい人
- クラシックや高音の繊細さを求める場合はやや不向き
- 「とりあえず使ってみたいけど、変なものは買いたくない」慎重派の方
MR5はこんな人におすすめ
- 音楽制作やDTMなど、制作用途を意識している人
- Bluetooth(LDAC)などワイヤレス再生を積極的に使いたい人
- 大音量・迫力のある低域を求める人
- 広めの部屋やリビングで使いたい人
- 「MR4以上の精度」で音を楽しみたい人
- 予算に余裕があり、長く使えるスピーカーを探している人
まとめ|MR5登場後でもMR4は“買い”の一台
最新のMR5が登場したことで注目が集まっていますが、MR4の価値は決して色あせていません。
むしろ「Bluetoothが不要」「価格を抑えたい」「デスクで快適に音楽や作業用BGMを楽しみたい」というニーズに対しては、今でもMR4がベストな選択肢です。
1年以上使って実感したのは、価格以上の満足感とバランスの良さ。
ズンズンと楽しく鳴る低音、クリアなボーカル、長時間でも疲れにくい高音域。さらにシンプルなデザインと設置のしやすさは、初めてのモニタースピーカーとしても安心しておすすめできます。
もちろん、制作やBluetooth利用まで求める方にはMR5が魅力的です。しかし、日常のリスニングや動画視聴、作業用BGMといった「リアルな使い方」にフォーカスすれば、MR4は依然として“ちょうど良い名機”です。
結論:
迷っているなら、まずはMR4を選んでみてください。きっと「スピーカーで音を聴く楽しさ」を初めて実感できるはずです。
有線での安定感と価格以上の音質、そしてデスクを引き締める存在感──MR4は今でも十分に“買い”です。